2024年度FDP臨床研究会 第10回 例会 令和7年3月15日(土)
2024年度令和7年3月15日(土)にFDP臨床研究会第10回例会をタカラベルモント・TB-SQUARE osaka内 3階フレキシブルセミナールームにて行いました。
🖊️ 座長は中村唯浩先生、演者は寺野和也先生•岩崎武史先生•高田秋介先生の3人の先生による発表でした。
🦷(寺野先生)
ジルコニアの接着について。近年マルチレイヤーのジルコニアディスクや超高透光性ジルコニアの登場によって強度面や審美面からラミネートベニアや接着性ブリッジなどに使用されています。補綴物をセットする際の正しい接着面の処理と適切な接着材料について講演して頂きました。
🦷(岩崎先生)
人生100年時代 若年者の欠損をどう捉えるか。26歳女性、左下7の欠損補綴について、基礎資料を採得し、しっかり分析した後、患者の現時点での最良の治療である智歯移植を選択した素晴らしい内容でした。
🦷(高田先生)
IODのその後。約10年前に行った、上顎は部分床義歯、下顎はショートインプラントを4本使用したIODで、ゴシックアーチを用いて顎位の決定を行ったデンチャーケースの治療計画、治療手順、経過を現在の状況の口腔内写真も対峙してプレゼンして頂きました。
今回、会場には25名・ZOOMでは12名の先生方にご参加いただきました🙇♂️
今回で今年度の例会が最後となりました。
次回は4月19日(土)で2025年度最初の例会となります。総会と池岡会長による基調講演です。次年度もご参加宜しくお願い致します😌






2024年度FDP臨床研究会 特別講演 令和7年2月15日(土)
令和7年2月15日(土)2024年度FDP臨床研究会特別講演をタカラベルモント・TB-SQUARE osaka内 3階フレキシブルセミナールームにて行いました。司会・座長は森川先生でした。
今年度は大阪市浪速区でご開業されています、鶴歯会主宰の岡崎英起先生をお招きして、会員限定、会場開催のみで2時間、『次世代の歯科医師へのアドバイス』というテーマでご講演して頂きました。
FDPはここ数年、卒後間もない若手の先生の入会が増え、基礎臨床コースの開講など次世代の先生の育成、指導に力を入れています。その先生方含め、中堅、ベテランの先生も原点回帰するため、岡崎先生の歯科医師人生をざっくばらんに話して頂きました。
歯科医師になられてから30年以上、常に色々なことにチャレンジされ、目標を掲げ、努力をされ、患者様にその知識、技術を提供して、なるべく患者の歯を守る、保存することを考えて治療されてきた長期症例のケースを拝見し、会員の先生にはとても勉強になった講演になりました。
今回、会場には53名の先生方にご参加いただき活発なディスカッションでご来場いただいた先生方にとっても非常に学びの多い1日になりました。
次回例会は3/15(土)です!
座長は中村唯浩先生、演者は寺野和也先生・岩崎武史先生・高田秋介先生です🦷
例会後は懇親会も予定しておりますので奮ってご参加ください😊






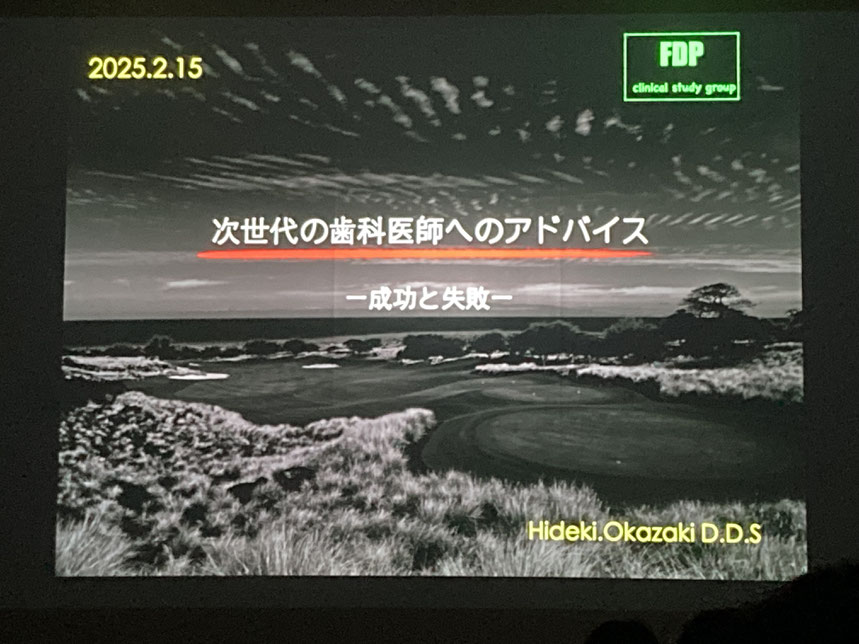

2024年度FDP臨床研究会 第9回 例会 令和7年1月18日(土)
2024年度令和7年1月18日(土)にFDP臨床研究会第9回例会をタカラベルモント・TB-SQUARE osaka内 3階フレキシブルセミナールームにて行いました。
🖊️ 座長は久保裕睦先生、演者は森川貴史先生•洪在潤先生•藤森啓先生の3人の先生による発表でした。
🦷(森川先生)
矯正治療における歯牙移動のメカニズムと、実際のご自身のインビザラインを用いた包括的な症例からさまざまな注意点と改善方法をご説明いただきました。ブラケットとマウスピースでは手法は違えど、基本的な考え方や適切な診断力という部分では等しく重要であることを再確認するよい機会となりました。
🦷(洪先生)
様々な学会で学び得た、知識と考え方•診断力を一つのCASEを通して発表いただきました。
基本を忠実に行い、最適な治療を行う事の重要性がご参加いただいた先生方にも伝わる内容でした。
🦷(藤森先生)
インプラント治療による咬合機能の回復により病的進行を抑制できたCASEを発表されました。一つ一つの資料を丁寧にまとめ上げ、分析し治療介入する。治療後の口腔内の改善が非常に綺麗な症例発表でした。日々の臨床での資料•分析のデスクワークが非常に重要であることが会場にも伝わったと思います。
今回、会場には27名・ZOOMでは19名の先生方にご参加いただきました🙇♂️
次回は2月15日(土)、岡崎英起先生をお招きした特別講演となります。終了後は懇親会も予定しておりますので、奮ってご参加下さい😌




2024年度FDP臨床研究会 第8回 例会 令和6年12月21日(土)
12/21に2024年度、第8回例会をタカラベルモント・TB-SQUARE osaka内 3階フレキシブルセミナールームにて行いました。
🖊️ 座長は渡辺茂文先生、演者は前川誠志先生・森雄基先生・小松啓之先生の3人の先生による発表でした。
(前川先生)
顎関節の解剖学的構造から各顎関節症の診断と治療へのアプローチを実際のケースを踏まえて分かりやすく
レクチャーいただきました。開口障害の術前後の劇的な変化に皆、大きな衝撃を受けました。
(森先生)
基礎資料の収集と正確な診査・診断・治療計画の立案から導き出された方針を患者の生活背景も考慮し
最小の治療介入で最大限のQOLの向上を求めるための接着性ブリッジの臨床応用を文献を交えて講演
いただきました。
(小松先生)
全顎治療においてデジタルの活用は臨床スピードを向上させ、良い結果をより早く提供できる効果があるが
重要となるのは症例に対しての深い診断力とアナログでも行っていた手法での技術理解が重要であり、
これらをもって新しい技術の効果を最大限に発揮できることを実際の症例を踏まえてレクチャーいただき
ました。
今回、会場には43名・ZOOMでは11名の先生方にご参加いただきました。
次回例会は来年の1月18日(土)です



